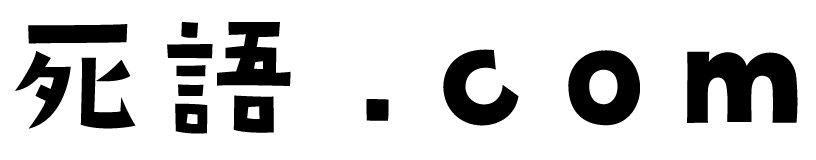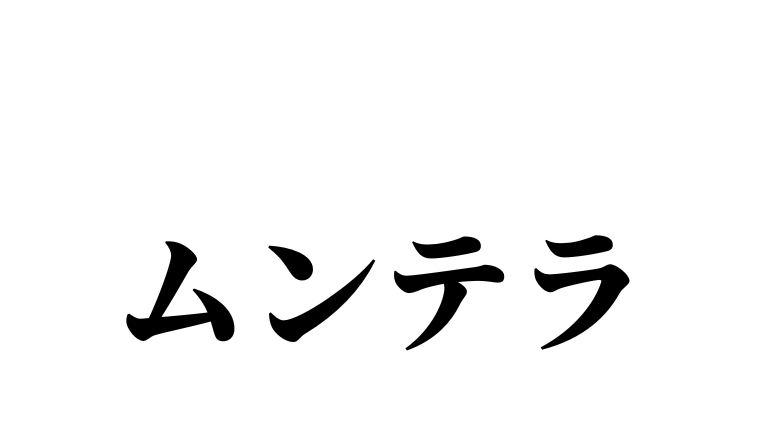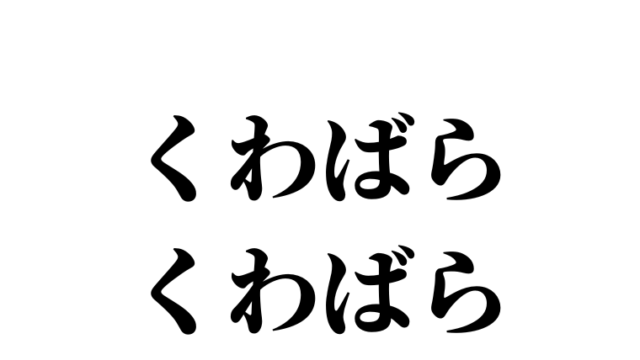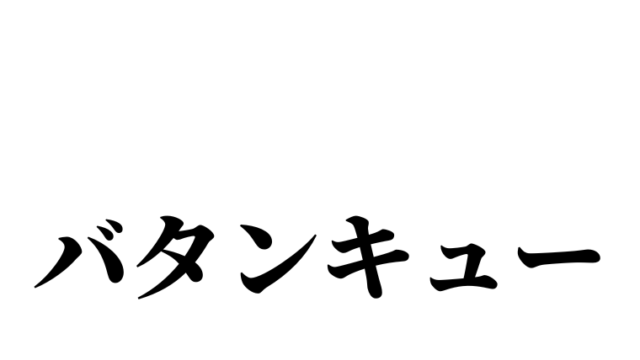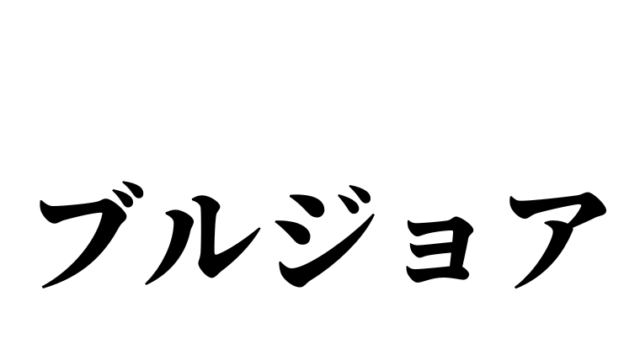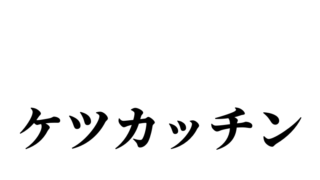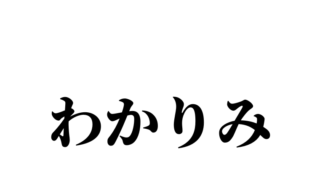意味
「ムンテラ」は医療用語で、ドイツ語の「MundTherapie」から派生した和製ドイツ語です。
Mundは「口」、Therapieは「治療」を意味し、医師から患者さん、もしくは家族に、現在の病状や今後の治療方針などを説明することを指します。
同じような意味の言葉に、「インフォームドコンセント(informed consent:IC)」があるのですが、こちらは説明すること(inform)だけではなく、同意すること(consent)という意味が含まれているため、ニュアンスが少し違います。
患者さんや家族の同意が必要な場合には、「インフォームドコンセント」を使用します。
「ムンテラ」はいつから使われているのか?
調べてみたところ、1963年に「むんてら」という本が出版されており、かなり古くから医療現場で使われている言葉だということがわかります。
また、ムンテラという言葉をポジティブに捉え、積極的に使っている人もいれば、使わないように進言している人もおり、医療現場でも評価が割れている言葉であることがわかりました。
だから、看護師に言い直されながら、今日も「患者さんの家族にムンテラするよ」と言い続けるのである。きっと「はい、分かりました。ICですね」と返されるのであるが。
なんとしても「ムンテラ」という言葉は死語にすべきだと私は思っています。
「ムンテラ」はいつ死語になったのか
1990年代後半あたりから、日本で医療訴訟のリスクが高まりました。
医師が訴えられることを回避しようとして、「医師が情報提供し、患者が治療方針を決める」という意味の「インフォームドコンセント」が使われるようになりました。
が、今でも患者に寄り添う意味での「ムンテラ」を愛用する医師も多いようで、完全に死語化したわけではなさそうです。